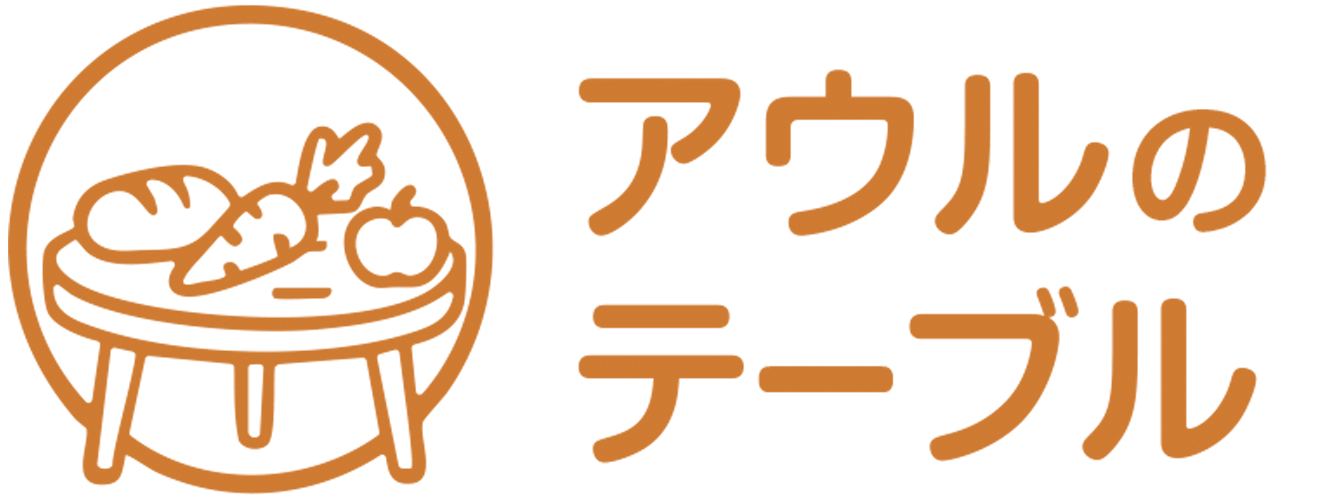夏の味覚として親しまれているとうもろこし。その中でもひときわ特別なのが、茨城県土浦市の野本農園で育てられている「白いとうもろこし・プラチナコーン」です。
真っ白な粒と果物のような甘さで、多くの人を魅了してきました。
今年の夏も多くの方に楽しまれたこの特別なとうもろこしについて、その特徴や栽培のこだわり、そして美味しい食べ方をご紹介します。
なぜ「白いとうもろこし」を作り始めたのか
野本さんが白いとうもろこし・プラチナコーンを作り始めたのは、実際に育ててみて、その美味しさに驚いたことがきっかけでした。
想像を超える甘さとみずみずしさ、かじった瞬間に果汁が飛び散るようなジューシーさに、「これは多くの人に味わってほしい」と感じたといいます。

プラチナコーンはまだ流通量の少ない希少な品種です。だからこそ「他ではなかなか出会えない特別なとうもろこしを届けたい」という想いが強まり、本格的な栽培を決意しました。
今では野本農園を代表する看板商品として、多くのリピーターに愛されています。
栽培から収穫までの流れ
プラチナコーンの栽培は、2月の種まきから始まります。3月には苗を畑に植え付け、冷え込みから守るためにビニールトンネルを設置します。

これは春先の寒さに弱いとうもろこしを守り、6月以降に出荷できるようにするための大切な作業です。
生育が進むと、高さは2メートルを超えるほどに成長します。日差しをたっぷり浴びながら育つプラチナコーンは、収穫時期を迎えると糖度がピークに達します。
野本農園ではそのタイミングを見極め、一つひとつの大きさを測り、さらに重さも計測します。出荷されるのは、野本さん自身が「これなら自信を持って届けられる」と思えるものだけです。
独自の工夫とこだわり
野本農園が特に大切にしているのは「土づくり」です。
プラチナコーンの甘さと美味しさを引き出すため、完熟発酵鶏糞堆肥をたっぷりと投入し、米ぬかや自家製の籾殻くん炭を加えて、ふかふかの土を育てています。
そのおかげで化学肥料や農薬の使用量は半分以下に抑えられ、安心して口にできるとうもろこしが実現しています。
さらに、出荷までの管理も徹底しています。茎が風で倒れないようにひとつひとつひもで支えたり、収穫後は鮮度を保つために素早く処理したりと、細やかな作業を欠かしません。
こうした努力が、粒の透明感やフルーツのような甘みを際立たせています。
苦労したことと挑戦
プラチナコーンは育てるのに手間がかかる品種です。
春先の寒さ対策はもちろんのこと、過去には発芽率の低い品種に挑戦し、1200株まいてもわずか10株しか芽が出なかったこともありました。それでも諦めずに工夫を重ね、現在の品質を築き上げています。

また、農薬を極力使わないため、病害虫への対応も簡単ではありません。
日々の見回りや手作業での管理が欠かせませんが、それでも「食べる人に安心して楽しんでもらいたい」という想いが原動力になっています。
白いとうもろこしの美味しい食べ方
プラチナコーンを美味しく味わう秘訣は「新鮮なうちに食べること」です。
収穫後は時間が経つにつれて糖度が下がってしまうため、届いたらできるだけ早めに召し上がるのがおすすめです。
最も手軽で美味しいのは、皮をむいてラップで包み、電子レンジで加熱する方法です。
その後、冷蔵庫でしっかり冷やすと、ひんやりとした甘さとシャキシャキの食感が際立ちます。サラダや冷製スープにしても、フルーツ感覚で楽しめるのが白いとうもろこしならではの魅力です。
まとめ
「白いとうもろこし・プラチナコーン」は、ただ珍しいだけでなく、野本農園の手間ひまと工夫が詰まった特別なとうもろこしです。
美しい粒と、果物のような甘み。その裏には、安心して食べてもらうための真摯な取り組みがあります。
白いとうもろこしは収穫できる時期が限られているため、まさに“旬を味わう贅沢”。毎年楽しみにしてくださる方も多く、販売開始とともに人気を集める一品です。
来たるシーズンには、ぜひ野本農園の白いとうもろこし「プラチナコーン」で、夏の恵みを味わってみてください。
📌【関連記事】野本農園の就農のきっかけと農業の始まり
野本農園の商品を見る>