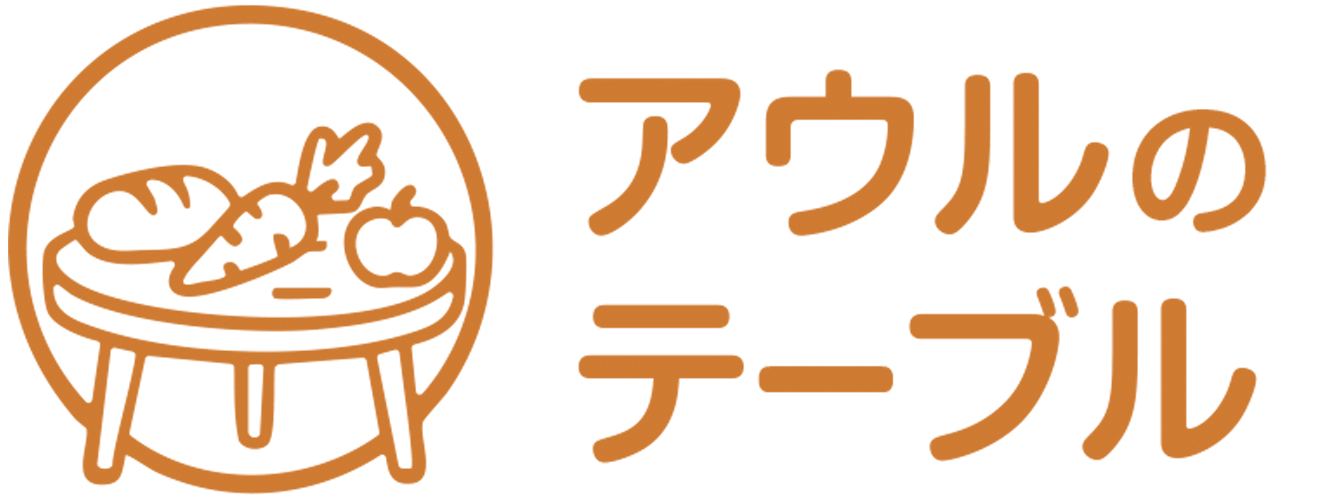昨今、米の価格高騰、備蓄米の放出といったニュースやSNSが世間を賑わせています。
「米が高すぎる」「なぜこんな値段になった?」と、消費者の戸惑いや不満の声も増加しています。
そこで今回は、生産現場で実際に米を作る農家さんにインタビューを行い、生産者としてのリアルな意見を伺いました。
米価の適正価格とはどれくらいなのか、生産現場のリアルな事情とはどのようなものなのか、ハナワ農産の塙和真さんに率直な考えをお聞きしました。

ハナワ農産のご紹介
今回インタビューに応じてくださったのは、ハナワ農産 次期3代目の塙和真さん。
関東一の米どころと呼ばれる千葉県香取市で、おじいさまの代から続く米農家です。
塙さんは現在、コシヒカリ、ふさおとめ、そして千葉の三大銘柄のひとつ**「多古米」**を育てています。
農薬や化学肥料の使用をなるべく削減し、精米時にとれた米ぬかや稲わらを使用した「循環型農業」を実践。
さらに、色彩選別機の導入や低温貯蔵によって、高品質なお米を年間を通じてお届けしています。

ハナワ農産 – 産直アウル
生産者のリアルな視点から見た現在の米価格の適正とは
最近のお米の価格について、消費者の中には「高すぎる」と感じる方も多いでしょう。
しかし塙さんはこう語ります。
「消費者が5kg4000円台のお米を『高い』と感じるのも理解はできる。ただ、農家の立場から言えば、2000円台という価格では私たちの収益としてはかなり厳しいんですよね。」
人件費、燃料代、肥料代といった経費をすべてまかなうには、2000円台では到底足りないとのこと。
さらに、兼業農家は作付面積が小規模でも農業機械の価格は同じため、負担が大きくなります。精米時の手数料や仲介料も重くのしかかります。
実際、消費者が「高い」と感じている価格でも、農家に届く利益はその数割にも満たないのが現状です。
最低賃金や経費は上がっているのに、米の値段が下がり続けている――この構造が米作りの持続可能性を脅かしています。

なぜ米の価格が高く感じられるのか?
塙さんは、米価の高騰の背景として次の要因を挙げます。
- 減反政策の影響
- 物価の高騰
- 米農家の減少
- 人件費の高騰
「米の生産は本当にコストがかかります。肥料や燃料、人件費が軒並み高くなっているので、生産コストが上がれば販売価格にも反映せざるを得ない。」
つまり、消費者が目にする米価の上昇は、農家の利益増ではなく、生産や流通にかかるコストの上昇によるものです。
転売ヤーによる米価格の高騰と生産者の心情
昨今話題になった、転売ヤーによる米の買い占めや再販売問題。
塙さんの見解はこうです。
「買ってもらえること自体はありがたいけど、極端な高値で消費者に届くのは良くない。品質が保たれないまま売られるリスクもある。」
特に産地や品質を信じて買ったお米が、管理不十分で味が落ちていたら消費者にとっても残念な経験です。
だからこそ、塙さんは色彩選別機で品質を保証し、低温貯蔵で鮮度を維持する取り組みを続けています。
消費者と生産者が望ましい関係を築くために
塙さんは次のように訴えます。
「農家も消費者も、適正価格を目指す必要がある。流通やコストの課題に向き合いながら、消費者が安心して美味しい米を手に入れられる環境を作りたい。」
消費者が米価の背景を理解し、生産者と協力して良好な関係を築くことが、米作りを持続可能にする鍵です。

まとめ
- ハナワ農産は25年以上、循環型農業と品質管理で安定した米作りを継続。
- 米価の上昇は農家の利益増ではなく、生産・流通コストの上昇が要因。
- 転売による価格高騰や品質低下のリスクがあるため、信頼できる農家から直接購入することが重要。